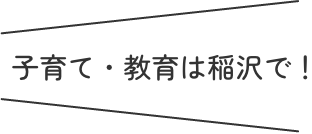電動生ごみ処理機の記録
- [更新日:]
- ID:2001
平成27年6月4日 市民の方より、電動で生ごみを分解できる電動生ごみ処理機を寄付していただきました。この電動生ごみ処理機は、微生物のちからで生ごみを発酵させ、分解します。資源対策課では、環境センター玄関で段ボールコンポストでの生ごみの堆肥化実験とあわせ、電動生ごみ処理機での生ごみの分解実験を行っています。
なお、生ごみ処理機の購入をお考えのかたは、市内登録店でご購入された場合、購入金額の3分の1(補助限度額 2万円)を補助いたします。詳しくは下記のページをご覧ください。

6月4日
電動の生ごみ処理機を環境センター玄関に設置しました。電動生ごみ処理機の中身は、市販のバイオチップが入っています。このチップ(土壌)を生ごみ処理機の内部装置で温度調節を行い、微生物の活動を活発にさせます。説明書によると、使用開始から生ごみを活発に分解処理できるようになる(微生物を育てる)までに5~10日かかるようです。


6月5日
いきなり問題発生です。頂いたバイオチップは、年数が経過して劣化しており、開始2日目にも関わらず、生ごみ処理機からチップ交換のサインが出てしまいました。そこで、バイオチップの代わりに段ボールコンポストの材料となっているピートモスとくん炭を投入しました。来週から生ごみの投入を開始したいと思います。


6月8日
電動生ごみ処理機をセットして4日間が経過しました。微生物がバイオチップ(基材)に住みついたと思いますので、生ごみの投入を開始していきたいと思います。まずは、バナナの皮・卵の殻・野菜の切りくずを投入しました。

6月9日
今日も野菜の切りくず等の生ごみを投入しました。段ボールコンポストでは分解されずらかったタマネギの皮を入れたので、分解できるか楽しみです。電動生ごみ処理機はふたを閉じると回転板が自動で回り、手で土を混ぜる必要はありません。下記画像は生ごみを投入し、自動でかき混ぜられた(撹拌された)状態です。


6月10日
今日も野菜の切りくずに加え、梅の実やエノキの根の部分などの生ごみを投入しました。生ごみ処理機の中の土を触ってみるとあたたかくなっていました。電気を使用し、微生物が繁殖しやすくなるよう保温しているのでしょうか。


6月18日
今日は、タマネギの皮や、インスタントラーメンの茹でた後の麺の切れ端や、庭に生えていた少量の雑草を投入しました。米や小麦粉などの炭水化物は微生物が好むため、すぐに分解されます。

6月23日
今日は、みかんの皮や、茶殻、卵の殻などを投入しました。電動生ごみ処理機の中を、あえて手でかき混ぜてみると、ごぼうの先端部分のかたまりや、鳥の骨などは分解されずにそのまま残っていることを確認しました。また、抗菌作用があるタマネギも、やはり分解されにくいようです。以前投入した野菜の葉やバナナの皮などは、ほぼ形が残っておらず分解されていました。

6月24日
今日は、恐らく微生物のちからでは分解できないあさりの貝殻を入れてみました。貝殻のかたちは残ると思いますが、何か変化が現れないか試験的に入れてみることとします。これまでに生ごみをたくさん入れた影響かわかりませんが、生ごみ処理機の中は非常に湿っており、熱くなっていました。

6月29日
生ごみ処理機の中を確認すると、草や野菜くずなどの水分を多く含むものは分解されてカリカリの繊維質だけが残っていました。やはり、あさりの貝殻はそのままのかたちで残っています。画像はありませんが、今日はじゃがいもの葉を大量に投入しました。

7月1日
問題発生です。電動生ごみ処理機から土の交換サイン(もしくはエラー)が再び出てしまいました。恐らく、一度に大量に投入したじゃがいもの茎と根が原因だと思われます。固い茎の部分を手で取り除き、バイオチップの代わりにピートモスとくん炭を継ぎ足しました。※推奨はしません。