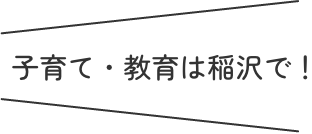稲沢のむかしばなし 余興の好きなお薬師さま(稲沢市高御堂町)
- [更新日:]
- ID:2614

稲沢市の中央部にある高御堂町につたわる「余興の好きなお薬師さま」と言うおはなしです。
「おっかぁー。歯がいたいよう。」
「ああそうかい。よしよし、そんじゃ、お薬師さまんところへいってこうなあ。」
むかし、むかし、今の国府宮駅の南に、薬師如来がまつってあった。歯痛に、ふしぎとよくきく仏さまだということで、村の人たちは、みんなおまいりに行ったということじゃ。
そして、毎年10月8日の命日には、供養のあと必ず、しし芝居などの余興をやっておった。
また、その近くには、三人が両手を広げてやっとかかえられる程の「えの木」があり、いくさの時にもこの木だけは残っておった。
さて、今から二百年程前のある年の命日のことだった。この年は天気が悪くてな。特に、お米の出来が良くなかった。
「なあ、村の衆、今年は供養のあとの余興は止めにすべーか。」
「ああ。こんな不作じゃ、しかたあんめい。止めにすべー。」
ところが、次の日、小雨がパラパラ降っておったが、突然「えの木」がパチパチと音をたてて、もえあがった。
火を消したかと思うと、すぐパチパチと燃え上がってしもうた。これを見た村の人は、「これはきっと、余興をやらなんだで、お薬師様がおこりなすったにちがいねぇだ。」と。
さっそく余興をし、お薬師さまの怒りをしずめた。それからは、欠かすことなく行われるようになったそうじゃ。