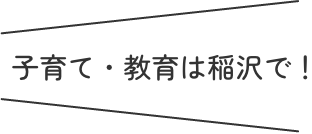稲沢のむかしばなし 鉄砲の名人と弓の達人
- [更新日:]
- ID:2591

日本の国を、まだおさめる人がいなくて、あちこちで、いくさがあったときの、お話です。
このときを、戦国時代といいますね。
稲沢市の南東にある清洲のとのさまと、岩倉のとのさまは、まえまえから、なかが悪く、よくけんかをしていました。
ある年の、あついなつのことです。
とうとう、清洲のとのさまと、岩倉のとのさまが、いくさをはじめてしまったのです。
二つの軍は、それぞれ三千人の兵(いくさをする人)をひきつれ、田畑をふみあらし、きりあい、うちあうなど、殺しあいをした。
清洲の軍には、「橋本一把」(はしもといっぱ)という、てっぽうの名人がいました。一把は、稲沢の西の方にある片原一色のおさむらいで、てっぽうのじゅつを心えていました。このいくさでも、大きな手がらをたてようとはりきっていました。
一方の岩倉の軍には、「林弥三郎」(はやしやさぶろう)という弓の達人がいました。
二人は、ともにすぐれたおさむらいさんであったので、おたがいの顔をしっています。
さきに声をかけたのは、弥三郎のほうであった。
「やあー、やあー。われこそは、弓の達人、林弥三郎であるぞ。きさまは、てっぽう使いの名人、一把とみたぞ。いざ、しょうぶ」
「いかにも、われこそは、てっぽうの名人、橋本一把なるぞ。みどもは、世にきこえた弓の達人ならば、生かしてかえらすわけにはいかない。きょうこそは、おいのちを、ちょうだいだあー」と、一把
「いざ、しょうぶ」
「さあ、かかってこい」と二人のしょうぶは始まった。
弓の達人は、いちばん大きな矢をつがえて、弓を力のかぎり強くひいて放した。
うなりをたて、その矢は一把の脇の下へ、ふかぶかとくいこんだ。
一把の顔は、いたみをこらえているのか、ゆがんでいるが、一把のもっているてっぽうから、火がふいた。
”ズドーン”
てっぽうには、二つの玉が、こめられていた。
弥三郎は、おなかをうちぬかれて、そのばにドッとたおれた。このあと、弥三郎の首は、清洲のおさむらいに、とられてしまいました。
二人のしょうぶは、あいうちとなりました。しかし、このいくさは、清洲のとのさまの勝ちになった、ということじゃ。
二人のおさむらいは、自分の力をほこっていましたが死んでしまった。そして、いくさのあった田畑は、ふみあらされ、血にそまったということです。
このようないくさが、あちこちでくりひろげられたのち、天下がとういつされた。