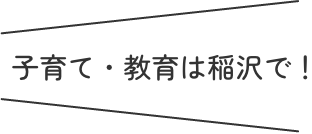稲沢のむかしばなし 長割千し(稲沢市片原一色町)
- [更新日:]
- ID:2586

『一色よいとこ、割干しどころ、細てつづくが、見せどころ・・・・・・』
片原一色町では、昔から、この『一色音頭』が、部落中でうたわれていました。
割干しとは、大根を縦に切り、干したもの。稲沢の名産で、全国的にも、ゆうめいです。
これは、いろいろな人が、大根をじょうずに切り、長い割干しを作るお話です。
江戸時代の終わりごろ、一色に、三輪為吉という人がいました。為吉は、割干し作りに力を入れていました。
「いままで、だれもみたことのない、でっかい割干しを作ってやろう」といって、大根を縦に切ったり横に切ったりしていました。いくにちもくりかえしているうちに、「できたぞうー」と、とつぜん大きな声をあげました。
こうしてできた長割干しを、名古屋の市場に出しました。市場の人は、2m半もある長割干しを見て、
「こらぁ、割干しのオバケだぁ」、「こんなものどうやって食べるんだろう」とか、「こりゃとても食べれんぞう」
為吉は、くろうして作った長割干しを、市場のみんなから、ひどくいわれ、
「なんのためにくろうしてきたんだ。もう二度とつくるもんかい」
それいらい、為吉は、ガックリきて、ねこんでしまった。そして、げんきになってからも、割干し作りをしなかったそうです。
それから30年ほどたち、明治時代になりました。こんどは、為吉のとなり村に、倉見岩之亟(いわのじょう)という若者がいました。この若者も、長い割干をじょうずに作ろうと、いろいろやっていました。
「うまくできないなあ」「こまったなあ」と、なやんでいました。
ところがある日、若者は、『まきずし』を食べました。そのとき、まきずしのまん中にいれてあるしんが、長割干しににているのにきがつきました。
「そうだ。これをまねればいいのだ」と、ひとりごとを言いました。そして、その『しん』の作り方を、おかあさんよりおそわりました。おしえてもらったとおり、大根でやってみたが、おもうようにいきません。
「まきずしのしんとは、ちょっとちがうなあ。むずかしいよ、おっかあ!」
ますます、若者はかんがえこんでしまうのでした。
あるとき、若者は、おなかにオデキができ、ねこんでしまいました。が、とつぜん
「おっかあ、はよう大根とほうちょうをもってこい。それに、竹のはしもだぞう!」
と大声でさけんだ。
おっかあは、
「おいおい、岩之亟。何をとつぜん言いだすのじゃ」「だいじょうぶか。しっかりせいよ」
かんびょうしていたおっかあは、岩之亟が気がくるったのかと思いました。おっかあは、しんぱいになり、畑にいっているおっとうをよびに、家からとびだして行きました。
畑から帰った、おっとうは、
「岩之亟おちつけ。おっとうだぞ。わかるか」と岩之亟に近よりました。
岩之亟は、
「おれはしょうきだぞ。とにかくはようほうちょうと大根をもってきてちょ」と、いたい体をおこして、ふとんの上にすわり、さけびました。
おっかあがもってきた大根とほうちょうで、まず、大根を『わぎり』にし、そして、そのまん中に、竹のはしをつきさし、わになった大根に、ほうちょうをあてて、ぐるぐるまわしていきました。
そうすると、大根は、どんどん長くむけていくではないか。
とうとう、2mの長い割干し大根ができあがりました。
「おっとう。おっかあ。できたぞ、長割干しが」と、とびあがってよろこびました。
そして、この長割干しは、時代のちがいか、市場でもひょうばんがよく、高くうれたそうじゃ。