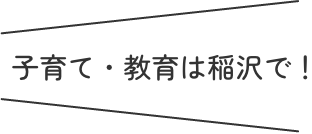稲沢のむかしばなし 茶ツボ行列(稲沢市稲沢町)
- [更新日:]
- ID:2585

『ずいずいずっころばし、ごまみそずい。茶ツボにおわれて、とっぴんしゃん。ぬけたらどんどこしょ・・』
みなさんも、この歌を聞いたり、歌ったりしたことがあると思います。江戸時代、京都から江戸の将軍様に、お茶を毎年さしあげていました。これは、歌にまでなった茶ツボ行列にまつわる話です。
立春から数えて百日あまりすぎると、江戸城から大きな茶ツボが京都の宇治まで運ばれます。宇治でつみとったばかりの新茶を茶ツボに入れ、それをまた江戸城まで運ぶのです。
茶ツボは、多くの人々によって守られて運ばれました。茶ツボ行列にあうと、大名でさえ、カゴをおろして、行列が通りすぎるのをまったほどでした。
いまの稲沢町のあたりは、稲葉宿とよばれていました。茶ツボ行列は、ときどき美濃路を通り、稲葉宿もそのとちゅうにある宿場の一つでした。
稲葉宿の東のはずれに、ケンタというガキ大将が住んでいました。ケンタは、近所のなかまを集め、毎日チャンバラをして遊んでいました。
「おれは赤胴鈴之助だ。みんなメッタ・メッタに切ってやる。ヤァー!」バシッ!バシッ!
「まてぇ、にげるか、ひきょうもの」
と、ケンタは、自分が赤胴鈴之助になったつもりで、わるいやつを切りたおしていきました。
ちょうしにのりすぎたケンタは、わるものを追いかけて美濃路まで出てしまいました。運わるく、ちょうど茶ツボ行列のおともの人にぶつかってしまいました。「ぶれいもの」の声が早いか、ケンタはバッサリと切られてしまいました。
「何も子どもまで切らなくてもいいのに」
「かわいそうなケンタ」
それから数年がたち、ふたたび茶ツボ行列が稲葉宿を通ることになりました。
それまで元気に遊んでいた子どもたちも、「茶ツボさま、茶ツボさまがみえるゾ!」という声を聞くと、家へわれ先にと帰っていき、戸をとざしてしまいました。お父さんから茶ツボ行列とケンタの話を聞いていたからでしょうか、物音ひとつしなかったということです。
そして、茶ツボ行列が通りすぎると、子どもたちはその分も遊んだといいます。『ずいずいずっころばし、ごまみそずい。茶ツボにおわれて、とっぴんしゃん。ぬけたらどんどこしょ・・・』といいながら遊んだ子どもたちの声が聞こえるようですね。