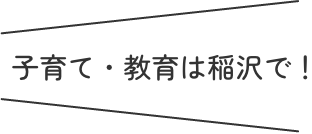稲沢のむかしばなし 川まつり(稲沢市日下部町)
- [更新日:]
- ID:2576

毎年秋になると、稲沢の東の方にある日下部町では、『水おとし』がおこなわれます。この話は、水おとしの日に、川で村の人たちがこいやふなをたくさんとるお話です。
日下部の神社には、秋になると、『10月1日水おとし』のはり紙がされます。
これを見た村人たちは、うきうきしながら、魚とりのじゅんびにとりかかりました。
魚とりのとってもすきな健太の家では、なやにある『どひょう』やあみなどをさがしはじめた。おっかあは、竹をわり、魚をさすヤリを作っていました。
いよいよ、水おとしの日がきました。
「おっかあ、はようおきんか。きょうは水おとしの日だぞ」と、朝早くから大きな声をあげていた。その横で妹のはるは、いつ起きたのか、マクラもとでにこにこしていた。ふたりは、大急ぎできがえをし、川へ走っていきました。
もう川には、たくさんの村人たちがきていた。
「いまから水を落とすぞー」と村のえらい人が大声をあげ、川の水をせきとめていた『とぶた(木の板)』をとりはらいました。すると、川の水が下の方へいっせいに流れ、みるみるうちに水面が10cm、20cmとさがっていきます。
フナがはねたぞー。ナマズもだ」と、村人たちは口々に言いました。そして、いっせいにタモやアミをもって川へ入った。
健太は、まず大きなウナギをつかまえようと、フナやナマズはそっちのけで、ウナギをさがしていた。
「いた。いたぞお。つ、つかまえたあ。もちきれんようおっとう」
その声を聞いた、健太のおっとうは、
「健太、いまいくからよう。しっかりつかまえとけようー」
「に、にげてしまうよう。はようきてくれおっとう」と、健太はひっしに2mもあるウナギをかかえながら、さけんだ。
そして、とうとうおっとうと、ふたりででっかいウナギをつかまえた。
いっぽう、妹のはるは、ピチピチはねるフナを両手でつかみ、とくいそうに、
「2ヒキもつかまえちゃったョ」とにこにこ顔でした。
こんなときの魚とりは、じょうずへたなんかなく、手を川につっこめば、フナやコイなどが、すぐにつかまります。だから、もっていったどひょうは、もてないくらいいっぱいになります。
健太も家のどひょうをもとうとしたが、
「こんな重てゃあ、どひょうなんか子どもがもてんぎゃ。おとながもたなあかん」とひとりごとを言いながら、せなかにせおおうとした。しかし、あまり重いので、川の中でひっくりかえってしまった。
せっかくつかまえたフナやナマズがにげ、健太はひっしでどひょうにもどしました。こんどは、おっとうとふたりで家にもって帰りました。
家では、おっかあがとれた魚を、クシにさして、焼きはじめた。
これを見ていた健太は。
「おっかあ、おらもてつだうよ」といってやり始めたが、なかなかおもうように、クシがささりません。
「イタッ。クシが手にささっちゃったあ」
手にクシをさしてから、健太はてつだいをやめてしまった。
こうして、クシにさした魚は、家ののきしたにつるし、かんそうさせました。そして、あとで、食べたいときに、『まぜめし』や『すし』に入れて食べたものでした。
健太の家でも、この夜はたくさんの魚のごちそうがならびました。中でも一番おいしかったのは、なんといっても、健太のつかまえた、大ウナギのかばやきでした。
「これは、おれがつかまえた、大ウナギだぞー」と、とくいそうに健太は言った。
この水おとしの日には、村をはなれて町に出ている人も、里帰りして魚をとるのでどの家も大にぎわい。それでこの日を「川まつり」とよぶようになったそうだ。