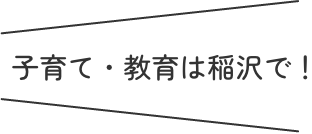稲沢のむかしばなし 行燈池(平和町嫁振)
- [更新日:]
- ID:2562

むかしむかし、嫁振の里に行燈池という名の池がありました。お盆が近づくと、里の人たちが、この池で行燈を洗ったのでそう呼ぶようになったということです。
里の長者の家には大ぜいのお手伝いさんがいました。その中に、おさよというとても美しい娘がおりました。いつもにこにこしていてよく働きましたので、里の若者たちは「おさよが大きくなったら、おらのお嫁さんにしたいなあ」と、思っていました。しかし、おさよは、それらの男たちには目もくれませんでした。それは、同じ長者の家で働いている富三という若者に心をよせていたからです。
富三は一番の早起きでした。「富三さん、おはようございます」と言って二番目に顔を洗いにくるのがおさよでした。富三は、働き者で心やさしくだれからも好かれていました。おさよが水くみをしているとそっと手伝ってくれたりしました。
そんな富三に、おさよの恋心はいっそうつのるのでした。
しかし、二人ともまだ若かったし長者の家で使われている身分です。富三も、おさよの気持ちは分かっていても、なかなか思うようにはいきませんでした。
そのころは、一年に一度お盆の七日に行燈を洗うならわしがありました。おさよも長者の言いつけで行燈を洗いに行燈池へ行きました。洗っているうちに、富三のことが頭に浮かんできて、ひとりでに顔が赤くなったりしました。
そんなとき、ふとしたはずみで洗っていた行燈が手からはなれ、池の中へ流れていってしまったのです。あわてたおさよが手をのばしたとたん、池に落ちてしまいました。池は底なしの泥沼です。都合の悪いことに、そのときはおさよのほかは誰もいませんでした。おさよは何度も富三の名を呼んでしまいました。
田んぼからの帰り道、富三が行燈池の近くを通りかかると、「富三さん」「富三さん」と、おさよが呼んでいるような気がしました。池を見ると洗いかけの行燈が浮いていました。そして「富三さん」と、またおさよが呼んだような気がしました。富三は、おさよが池に落ちて沈んでしまったんだとさとり、悲しみにくれました。
それからというもの、夜になると、この池から灯火があらわれて里の方へ来るようになりました。
その話を聞いた若者たちが元気に任せて見に行きました。するとその灯火は消えてなくなります。しかし、帰りかけるとまた灯火があらわれて里の方へ動いて行きます。これが何度も繰り返されるのです。
そんなことが続いたので、里の人は哀れに思いおさよの霊を慰めるために、池のほとりに小さな祠をたてました。それからは、もう灯火はあらわれなくなりました。
この行燈池も、昭和三十一年五月、近くの日光川の堤を直したときの残った土で埋め立てられてしまって今は田んぼに変わってしまいました。
しかし祠は、売夫神社の北西に「行燈之宮」として大切にお祀りされています。