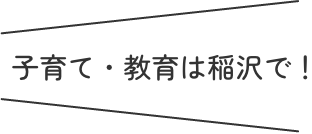稲沢のむかしばなし 稲葉そうどう(稲沢市稲沢町)
- [更新日:]
- ID:2552

江戸時代300年もついにおわり、明治の時代をむかえた。しかし、東京での政治改革は、まだ稲沢までつたわっていなかった。稲沢のほとんどを、清洲代官が、とりしきっていた。
まだ、サムライの時代がのこっていた、人々はふあんになっていた。このとき、米がほとんどとれなかったことを、きっかけに、農民たちが立ち上がった、お話です。
明治2年は、天気がわるく、大雨がつづき、川はあふれ、米はほとんどとれませんでした。こまった農民は、清洲代官に、年貢(いまのぜいきん)をまけて、農民にも、お米をわけてくれるよう、たのみました。しかし、代官は、ガンとしてこのねがいを、ききとろうとしません。はんたいに、役人たちに、しっかり年貢をとってこい、というしまつ。
農民たちは、この知らせを聞き、頭にきました。
「自分たちは、ゆうふくな家をたずねて、毎日おさけをにんであそんでいる。それなのに、ワシら農民は、あす食べる米もない」
12月21日、雪がふりはじめたころ。
農民たちは、カマや竹ヤリを手に手にとってあつまった。むしろハタを立て、稲葉へとむかった。
役人たちは、この日も、稲葉でいちばんお金もちの家にあつまり、おさけをのんであそんでおった。そこへ、とつぜん農民たちがおそってきたものだから、役人たちは、竹ヤリにつかれ、ほうほうのていで、にげていってしまった。
農民たちは、たてものをこわし、あるものは金をとってにげ、あるものは、となりのミソ屋にまでおしいった。こわされたタルからながれる・しょうゆは、ひとばんじゅうながれ、小さな小川をつくったという。
そのあと、お金もちのうちをつぎつぎおそっていった。
雪は、とうとう30センチもつもった。農民たちは、つぎの日、清洲の代官所へ、おしかけた。
しかし、代官所では、150人あまりの役人が、テッポウをもってまちかまえていた。
“ズドーン”“ズドーン”
農民たちは、竹ヤリでたたかいましたが、テッポウにはかてません。とうとう50人をこえる、ケガした人・死んだ人が出ました。農民たちは、バラバラに、にげていってしまった。
30人のたいほしゃを出して、この稲葉そうどうはおさまった。これに出た農民は35,000人といわれ、こわされた家は、80けんにものぼるという。