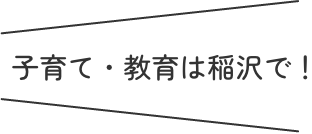稲沢のむかしばなし スズをまつる神社(稲沢市矢合町)
- [更新日:]
- ID:2530

矢合町の南をはしっている、八神街道ぞいにある『鈴置神社』につたわるお話。
あるあさ、矢合の西を流れている三宅川が大雨であふれたとき、村の少年が、旅人から教えてもらったほうほうで、村人たちを守る話です。
むかし、むかし、木曽川は、いまのように一本の大きな川でなく、何本にも分かれていました。三宅川もその一つで、むかし、広野川とよばれていました。また、いまより川はばも広く、水も多かったそうです。
そんなころのある年、雨がふりつづき、いまにも川があふれそうになりました。
そのようすを見ていたある村人は、
「オーイ、村のしゅう。川がきれるぞー」と、大きな声をだしながら、村中をさけんで走りました。それを聞いた村人たちは、集会所に集まり、土とふくろをじゅんびし、川へ行こうとしました。
そこへ、一人のみすぼらしい旅人が、ちっちゃなふくろを持って、通りかかりました。
「どなたか、こんばんとめてくれんかのう」
それどころではない村人たちは、だれ一人として、あいてにしなかった。
「すまねえが、たのむにとめてくれんかのう。このどしゃぶりだ、たすけるとおもって、とめておくれョ」と旅人は、もう一度たのみましたが、だれもへんじをしてくれませんでした。
旅人は、村人たちに、ていねいにおじぎをして、立ちさろうとしました。それを見ていた村の少年は、
「ねぇ、旅の人、おらのおっかあにたのんだる、ついてりゃあ」と言って、旅人をつれて、家に帰りました。
少年の家は、おっかあとふたりぐらしで、とてもまずしかった。しかし、旅人にはできるだけのもてなしをしました。
旅人は、
「とめてもらったうえに、こんなにごちそうをしてもらって、ほんとうにありがたあ」
と、旅人はたいそうよろこんだ。
その旅人は、むかし、川を守るしごとをしていた人で、大水がきたらどうしたらよいかを、少年に教えました。
あくる朝、旅人はおれいにといって、ふるびたスズが入ったハコをおいて旅だちました。
少年は、旅人から教えてもらったことを、村のえらい人に言いました。
「土のふくろを、きれたところへ入れとったっていかんョ。ふとい木もつかわにゃいかんぎゃあ」
村人たちは、そのとおりやってみました。するときれたところは、じょうずにふさがり、ひがいは少なくすみました。
村人たちは、少年にむかって、
「ええことを教えてくれた。おみゃぁは、えりゃあ。よう村をすくってくれた」と、ほめておれいを言いました.
それいらい、少年は、大雨がふったり、こまったときには、旅人がおいていったスズをおがんだ。すると、ふしぎなことに、いい考えがうかび、村人たちをよくすくいました。
そして、その少年は大きくなり、いっしょうけんめいはたらき、村のりっぱな人になりました。とくに、川を守ることに力を入れたので、二度と川があふれて、こう水になることはありませんでした。
ざんねんなことに、この人はなくなり、村人たちは、
「あの人の家にあるスズを、神社においてはどうかのう。おけば、ふこうは、きっとおこらんぞ」そう言って、そのスズを神社の守り神として、まつりました。
また、しんだあの人のみょうじが「鈴木」といったこともあってか、その神社を『鈴置神社』と言うようになったそうです。