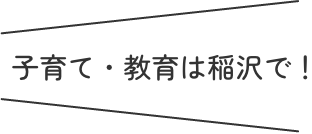稲沢のむかしばなし キツネの燈(稲沢市長野町)
- [更新日:]
- ID:2526

長野町に伝わる「キツネの燈」というお話です。
「さぁ、今日も天気がええで、キツネの燈がぎょうさん通るぞ。おまえら、お父の言うことをよう聞かんと、みんなキツネに食われちまうぞ」
昔、ばあちゃんが子どものころはなぁ、よくこう言うことを聞かされたもんじゃった。
それはな、夜になるとやみの中で、ついたり消えたりする、わけのわからん燈があってのう。それもひとつやふたつではなく、何十個もが重なって、行列をつくっとった。
それはな、ちょうどキツネがはねるように飛んでいく、姿ににとったなぁ。この燈は子どもにとっては、非常に不気味でなぁ。お父やお母からしかられるよりこわく、みんな家の中でガタガタふるえておったもんじゃ。
大声で泣いていた子どもも、急にだまったり、親の言うことをよく聞かんワンパンぼうずも、そりゃよう言うことを聞くようになった。
ほんでもな、子どもたちがおそれていたキツネの燈、実はなぁ、村人たちが手に持って歩く、ちょうちんの燈だったんじゃ。
昔は電燈がなかったもんで、油を燃やして、それを明かりとしとったんじゃ。
一日の野良仕事を終えると、村人たちが油を買いに行ってなぁ。そのとき、ちょうちんをもって歩いとったんじゃ。これが人の影になって見えたり、見えなかったりしとったんじゃ。
そんなことをしらん子どもたちにとっちゃ、こわいもんだったなぁ。ばあちゃんもそりゃあ、こわかった。
大正時代になって、電燈が各家にひとつだけついた。わずか16ワットの明るさだったが、ほりゃあもう、みんなびっくりしたもんだった。
当時の電気代は、一ヵ月わずか61銭だった。
それからは、キツネの燈はあまり、見られんようになったなぁ。