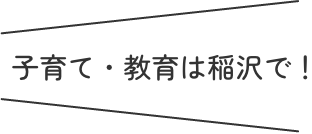快適で住みよいまちづくり条例
- [更新日:]
- ID:1007
稲沢市快適で住みよいまちづくり条例は、平成20年第5回稲沢市議会12月定例会で可決され、平成21年4月1日より施行されました。
添付ファイル
稲沢市快適で住みよいまちづくり条例とは
稲沢市快適で住みよいまちづくり条例とは、稲沢市環境基本条例の基本理念に基づき、野焼きや路上喫煙、空き地の雑草など生活環境の身近な問題について、市、市民等および事業者の役割を明らかにするとともに、それぞれがこの役割の下、生活環境の保全および美化の促進を図ることにより、市民等の快適で住みよい生活環境の確保に寄与することを目的としています。
稲沢市快適で住みよいまちづくり条例の説明
稲沢市快適で住みよいまちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、稲沢市環境基本条例(平成15年稲沢市条例第22号)の基本理念に基づき、生活環境の身近な問題について、市、市民等および事業者の役割を明らかにするとともに、それぞれがこの役割の下、生活環境の保全および美化の促進を図り、もって市民等の快適で住みよい生活環境の確保に寄与することを目的とする。
【趣旨】
本条例は、生活環境の身近な問題について基本的な事項を定めて、住みよい生活環境を確保する上で、市、市民等および事業者の役割を明らかにすることによって、市民等の快適で住みよい生活環境の確保に寄与するものです。
【解釈】
「生活環境の身近な問題」とは、空き缶等ごみの散乱、犬猫のふん、犬の放し飼い、落書き、路上喫煙、空き地の雑草、植木のはみ出し、ごみの放置、野焼き等により、市民等の生活に支障を生じさせることを言います。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、または市内を通過する者をいう。
(2)事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(3)空き缶等 飲食物を収納し、または収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器をいう。
(4)吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する空き缶等以外の物で、捨てられることによってごみの散乱の原因となるものをいう。
(5)公共の場所等 道路、公園、広場、河川、公民館その他の公共の用に供する場所をいう。
(6)犬、猫等 動物の愛護および管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項各号に掲げる動物をいう。
(7)落書き 公共の場所等を所有し、占有し、または管理する者の承諾を得ず、塗料等により、文字、図形若しくは絵柄を書くことまたは書かれた文字、図形若しくは絵柄をいう。
(8)喫煙 たばこを吸うことおよび火のついたたばこを所持することをいう。
(9)回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(10)野焼き 適法な焼却施設以外で廃棄物を焼却することをいう。
【趣旨】
この条例で頻繁に使用する基本的な用語について、その語句の表す意味を明確にしたものです。
【解釈】
1 第1号
「市民等」とは、市内に居住している者、市内の事業所に勤務している者、市内の学校に在学している者、市内に観光等で滞在する者、市内を通過する者を言います。
2 第3号
「空き缶等」とは、飲食物を収納するすべての容器を言います。
3 第5号
「公共の用に供する場所」とは、公共の施設であってその建物および敷地を言います。
4 第6号
「第44条第4項各号に掲げる動物」とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、いえうさぎ、鶏、いえばとおよびあひるを言います。
5 第10号
「適法な焼却施設」とは、構造基準に適合した焼却施設で、環境大臣が定める焼却の方法を守っていることを言います。
(市の役割)
第3条 市は、快適で住みよいまちづくりの推進に関する必要な施策を策定し、実施するものとする。
2 市は、前項の施策を策定し、実施するに当たっては、市民等および事業者の適切な参加の方策を講ずるとともに、快適で住みよいまちづくりの推進について、意識の啓発を図り、自発的活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
【趣旨】
市の行う必要な施策を実施するに当たり、その基本的な姿勢を明確にしたものです。
【解釈】
1 第1項
「必要な施策」とは、地域の生活環境を監視する者の設置や環境美化活動の実施などを言います。
2 第2項
「必要な措置」とは、第1項の施策を実施するに伴い必要な資材の提供と、その後の処理方法を言います。
(市民等の役割)
第4条 市民等は、快適で住みよいまちづくりの推進に対する意識を高め、積極的に生活環境の保全および美化の促進を図る活動に参加し、当該活動の充実に努めるものとする。
2 市民等は、市が快適で住みよいまちづくりを推進するために実施する施策に協力するものとする。
【趣旨】
市民等が、活動に参加するに当たり、その基本的な姿勢を明らかにしたものです。
【解釈】
1 第2項
「施策」とは、春・秋に実施されるごみゼロ運動を言います。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、事業所およびその周辺その他の事業活動を行う地域において、生活環境の保全および美化活動を推進するものとする。
2 事業者は、市が快適で住みよいまちづくりを推進するために実施する施策に協力するものとする。
【趣旨】
事業者は、事業所およびその周辺の美化活動を行うに当たり、その基本的な姿勢を明らかにしたものです。
【解釈】
1 第2項
「施策」とは、春・秋に実施されるごみゼロ運動を言います。
(空き缶等の放置および投棄の禁止)
第6条 何人も、空き缶等をみだりに公共の場所等に放置し、または投棄してはならない。
【趣旨】
ごみの散乱防止について定めたものです。
【解釈】
飲食物を収納し、または収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器を、道路、公園、広場、河川、公民館その他の公共の用に供する場所に放置すること、または投棄することを禁止しています。
(犬、猫等のふんの適正処理)
第7条 犬、猫等を飼養し、または保管する者(以下「犬、猫等の飼養者」という。)は、当該犬、猫等のふんを放置し、または投棄してはならない。
2 犬、猫等の飼養者は、飼養し、または保管している場所から当該犬、猫等を連れ出す場合は、ふんを処理する用具を携行しなければならない。
【趣旨】
犬、猫等のふんの適正な処理方法について定めたものです。
【解釈】
1 第1項
犬、猫等のふんの放置および投棄を禁止しています。
2 第2項
犬、猫等を連れ出す場合は、ふんを処理する用具を携行することを義務付けています。
(犬、猫等の適正管理)
第8条 犬、猫等の飼養者は、当該犬、猫等を公共の場所等において移動し、または運動させるときは、常に引き綱等により制御しなければならない。
【趣旨】
犬、猫等の適正な管理方法について定めたものです。
【解釈】
犬、猫等を散歩などで屋外に出すときは、常に引き綱等により制御することを義務付けています。
(落書きの禁止)
第9条 何人も、公共の場所等に落書きをしてはならない。
【趣旨】
落書きについて定めたものです。
【解釈】
公共の場所等の建物、構造物等に対する落書きを禁止しています。
(落書きの消去の要請)
第10条 市長は、落書きが放置され、著しく周辺の環境を損なう状態にあると認めるときは、当該公共の場所等の管理者に対し、当該落書きを消去するよう要請することができる。
【趣旨】
落書きが放置された場合の処置について定めたものです。
【解釈】
落書きが放置され、周辺の生活環境を著しく損なう場合は、管理者に対して落書きを消去するよう要請することを定めています。
(路上喫煙の禁止)
第11条 何人も、第17条第1項の規定により指定された路上喫煙禁止区域においては、定められた場所以外の場所では、喫煙をしてはならない。
2 何人も、吸い殻等をみだりに公共の場所等に放置し、または投棄してはならない。
【趣旨】
路上喫煙禁止区域における喫煙および、吸い殻等の投棄について定めたものです。
【解釈】
1 第1項
路上喫煙禁止区域では、指定された場所以外での喫煙が禁止となります。
2 第2項
たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず等を、公共の場所等に放置、または投棄することを禁止しています。
(喫煙者の義務)
第12条 何人も、公共の場所等において喫煙するときは、灰皿等のたばこの吸い殻を収納する容器が設置されている場所を利用し、または吸い殻を入れる目的とした専用の携帯用容器を携行し、これを使用するよう努めなければならない。
【趣旨】
公共の場所における喫煙者の義務について定めています。
【解釈】
道路等公共の場所においては、灰皿の設置されている場所で喫煙すること。それ以外の場所では、携帯用灰皿を携行し、これを使用することが努力義務となっています。
(回収容器の設置および管理)
第13条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)により容器入りの飲食物を販売する者は、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、当該回収容器を適正に管理しなければならない。
【趣旨】
自動販売機の管理について定めたものです。
【解釈】
自動販売機で容器入りの飲食物を販売する者は、回収容器を設置し空き缶等が散乱しないよう容器を適正に管理するよう義務付けています。
(公共の場所等におけるごみの散乱防止)
第14条 何人も、公共の場所等を汚さないようにしなければならない。
2 公共の場所等において、印刷物等を公衆に配布し、または配布させた者は、配布した場所の周辺に散乱している当該印刷物等を速やかに回収するとともに、これを適正に処理しなければならない。
3 公共の場所等において、催しを行い、または行わせた者は、当該催しを行った場所およびその周辺におけるごみの散乱を防止しなければならない。
【趣旨】
公共の場所等におけるごみの散乱防止について定めたものです。
【解釈】
駅周辺等で、広告物等を配布した者または、配布させた者は周辺に散乱した広告物を回収しリサイクルするなど適正に処理することを義務づけています。
(土地、建物および工作物の適正管理)
第15条 土地、建物または工作物を所有し、占有し、または管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、当該土地、建物または工作物を清潔に保持しなければならない。
2 土地所有者等は、当該土地に雑草が繁茂することにより、ごみ等の不法投棄を誘発し、害虫の発生源となり、または火災若しくは犯罪発生の遠因とならないよう、適正に管理しなければならない。
3 土地所有者等は、当該土地の樹木の枝が外部に侵出することにより、付近の生活環境を害することがないよう、適正に管理しなければならない。
【趣旨】
土地、建物および工作物の適正な管理について定めたものです。
【解釈】
1 第1項
土地、建物または工作物の所有者、または管理する者は、ごみ等が大量に堆積しないよう土地等を清潔に保持することを義務付けています。
2 第2項
土地所有者等は、土地に雑草が繁茂した場合、適切な時期に刈り取る等して適正に管理することを義務付けています。
3 第3項
土地所有者等は、生垣等の樹木の枝が道路等にはみ出し、通行の障害とならないよう、適正に管理することを義務付けています。また、樹木の枝が隣接土地にはみ出し、落ち葉により生活環境を害することも考えられます。
(野焼きの禁止)
第16条 何人も、廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の法令に定める場合を除き、野焼きをしてはならない。
【趣旨】
野焼きの禁止について定めたものです。
【解釈】
廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第14条により焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却が定められています。
1 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
3 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
この場合でも、周辺の住民から苦情があれば、指導の対象となります。
(路上喫煙禁止区域の指定等)
第17条 市長は、特に必要があると認められる区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。
2 前項の指定は、終日または時間帯を限って行うことができる。
3 市長は、路上喫煙禁止区域を指定し、変更し、または解除しようとするときは、当該区域の市民等の意見を聴くとともに、関係団体等と協議するものとする。
4 市長は、路上喫煙禁止区域を指定し、変更し、または解除するときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該区域であることを示す標識を設置する等周知するものとする。
【趣旨】
路上喫煙禁止区域の指定等について定めたものです。
【解釈】
1 第1項
不特定多数の市民等が集まる主要駅駅周辺の区域を、路上喫煙禁止区域として指定できます。
2 第2項
路上喫煙禁止区域は、終日または時間帯を限って指定できます。
3 第3項
路上喫煙禁止区域を指定し、変更し、または解除するときは、当該区域の市民等の意見を聴くとともに、関係団体等と協議します。
4 第4項
路上喫煙禁止区域を指定し、変更し、または解除するときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該区域であることを示す看板、道路標示標識を設置し周知します。
「規則で定める事項」とは、指定の区域の名称、指定の区域、指定区域内において喫煙をすることができる場所、指定の時間帯、指定する年月日、禁止行為をした場合の措置を言います。
(ごみの散乱防止重点地域の指定等)
第18条 市長は、市民等または事業者が積極的に美化活動に取り組んでいる地域をごみの散乱防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地域を指定し、変更し、または解除するときは、規則で定める事項を告示するものとする。
3 市長は、重点地域において、地域の自主的な美化活動を支援するものとする。
【趣旨】
ごみの散乱防止重点地域の指定等について定めたものです。
【解釈】
1 第1項
市民等または事業者が、清掃活動等を積極的に取り組んでいる地域を、ごみの散乱防止重点地域として指定できます。
2 第2項
重点地域を指定し、変更し、または解除するときは、規則で定める事項を告示します。
「規則で定める事項」とは、指定の地域の名称、指定の地域、指定する年月日を言います。
(ごみ散乱防止市民行動の日)
第19条 市長は、ごみの散乱防止について市民等および事業者の環境美化意識の向上と理解を深めるため、ごみ散乱防止市民行動の日を設けるものとする。
2 ごみ散乱防止市民行動の日は、毎年5月27日から6月2日までの間の日曜および10月の第3日曜とする。
3 市長は、ごみ散乱防止市民行動の日には、市民参加による事業を実施するものとする。
【趣旨】
ごみ散乱防止市民行動の日について定めたものです。
【解釈】
毎年春と秋の2回、ごみ散乱防止市民行動の日を設け、市内で一斉にごみゼロ運動を実施します。
春は、5月27日から6月2日までの間の日曜、秋は、10月の第3日曜となります。
(指導および勧告)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為を中止し、または是正に必要な措置を講ずるよう指導または勧告をすることができる。
(1) 第6条の規定に違反して空き缶等を公共の場所等に放置し、または投棄した者
(2) 第7条の規定に違反して犬、猫等のふんを適正に処理しなかった者
(3) 第8条の規定に違反して犬、猫等を引き綱等により制御しなかった者
(4) 第9条の規定に違反して公共の場所等に落書きをした者
(5) 第11条第1項の規定に違反して路上喫煙禁止区域で喫煙をした者
(6) 第11条第2項の規定に違反して吸い殻等を公共の場所等に放置し、または投棄した者
(7) 第13条の規定に違反して回収容器を設置せず、またはこれを適正に管理しない者
(8) 第14条第1項の規定に違反して公共の場所等を汚した者
(9) 第14条第2項の規定に違反して散乱した印刷物等を回収せず、これを適正に処理しなかった者
(10) 第14条第3項の規定に違反してごみを散乱した者
(11) 第15条第1項の規定に違反して土地、建物または工作物を清潔に保持しない者
(12) 第15条第2項および第3項の規定に違反して土地を適正に管理しない者
(13) 第16条の規定に違反して野焼きを行った者
【趣旨】
条例に規定された違反行為に対する指導および勧告について定めたものです。
【解釈】
条例に違反する行為を見つけた場合は、違反行為を中止し、または是正に必要な措置を講ずるよう口頭により指導します。
口頭による指導に従わない者には、文書により勧告をします。
(命令)
第21条 市長は、前条に掲げる者が同条の指導または勧告を受けて、正当な理由がなく当該指導または勧告に従わないときは、当該指導または勧告に従うよう命ずることができる。
【趣旨】
勧告に従わない場合の命令について定めたものです。
【解釈】
勧告を受けた者が、正当な理由がなく勧告に従わないときは、勧告に従うよう文書により命令をします。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
【趣旨】
本条例の施行に関して必要な事項は、市長が規則等で定めることとしたものです。