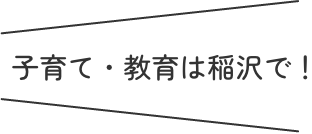平成19年度第6回市民参加条例策定委員会 会議録要旨(平成20年2月13日)
- [更新日:]
- ID:840

日時
平成20年2月13日、午後7時~9時30分
場所
稲沢市役所 第3分庁舎 第9会議室
出席者数
19名
政策アドバイザー2名・委員11名・市長公室長・事務局6名
(※政策アドバイザー1名は、委員を兼務しています)
傍聴者数
0名
※資料はページ下部でご覧いただけます。
1.協議事項
(1)条例案について(※資料1、2、3)
事務局より、条例の事務局案について1条ごとに説明を行った。
(事務局)前回までの議論を踏まえ、理念型と総合メニュー型を作成した。総合メニュー型は理念型に追加する形で作成しているので、総合メニュー型を使って説明したい。
(以下、説明の要点)
総合メニュー型の説明
- 1条(目的):「市と市民の責務を明らかにする」という文言を追加した。
- 2条2号(市民参加の定義):PDCAの各段階が明確となるよう変更した。
- 3条(基本原則):PDCAの各段階に共通する基本的なことを記述した。
- 4条2項、3項(市民の責務):市民同士の平等や意見交換を考慮した。
- 5条2項(市の責務):あえてPDCAの各段階のことを記述して明確にした。
- 6条1項5号(市民参加の対象):企画立案段階以外の市民参加を考慮して追加した。
- 12条(パブリック・コメント手続):要綱では記述していなかった具体的な方法について記述した。
- 13条、15条、16条:それぞれ新規に追加した。
〈※以下、特に断りのない限り、「(2)総合メニュー型」の条番号を使用〉
(委員長)事務局案について各自意見を言ってほしい。
(委員A)1条「目的」の条文が地味。市民参加の権利を少し入れた方がよいのでは?
6条3項の「前条」は、誤りか?
4条「市民の責務」に書かれている内容では、市民参加が難しく聞こえないか?
6条1項5号の「市民参加手続を経ることが適当と認められるもの」は、誰が適当と認めるのか?
(事務局)6条3項の「前条」は、誤り。訂正する。
6条1項5号の誰が認めるかということは、6条の最初に「実施機関は」と書いているので、市が認めると規定している。
(委員A)(「するよう努めなければならない」という語尾が多いが、「する」でよいのではないか。
5条でPDCA(企画立案、実施、評価)の各段階と言いながら、6条以降では評価段階の手続が欠落している。
13条「ワークショップ手続」と14条「開催記録の作成および公表」は1つの条にまとめた方がよい。
(委員B)(前回、私は総合メニュー型条例がよいと言ったが、やはり理念型では具体的なことが書かれていないので条例にするのは難しい。委員Aさんが言われたが、PDCAの各段階に分けても、実施段階と評価段階の手続を細かく書くのは難しいと思う。
文末にもう少し工夫がほしい。例えば、8条1項の「努めなければならない」は、但し書きで公表できない場合を記入しているので、必要ない。「公表しなければならない」でよい。
(委員C)4条(市民の責務)は文言が厳しい。「市が市民を利用する」と受け取れる。何のため、誰のための市民参加なのかを、前文で記入してほしい。今まで参加できなかった部分に参加できるのはいいことだが、その分、市民がやらなくてはいけないことも増える。しかし、参加できない部分も残っている。あいまいなものではなく、はっきりとした条例にしてほしい。参加できるならどこまでも参加できるとわかりやすい。
(委員長)条例の意義を前文で明らかにした方がよいという意見と、前文は不要で目的で示せばよいという意見があるようだが、ほかのご意見は?
(委員D)3条の「すべての市民」には、年齢が低い人も入ってくるのか?
4条の「積極的な市民参加」がなかったときは、どうするのか?
(委員E)アンケート調査が評価段階に当たるだろうかと思う。それでも、条例全体を見ると、やはり企画立案段階に偏っている。
(委員F)総合メニュー型の方が市民もわかりやすいのでは?
稲沢市の現状を考えると、もう少し評価段階についても具体的に書くべきだと思う。市民から見て肩透かしと思われるようなことはよくない。11条「審議会等の構成員」は、「多彩な意見を反映させるようにする」という文言が必要だ。
(委員G)委員Dさんが言われたように、市民が参加したくなるような仕掛けが要るのでは?条例の意味がわかるような“解説書”がいるのでは?
(委員H)6条2項「市民参加の対象としない」事項が具体的にどういうものか、不明瞭なことが気になった。
(委員I)条例を見たときに、「これができる」より「これをしなくてはいけない」のイメージだ。「こういうこともできる」という文言を入れないと、結局、市民参加が進まなくなってしまう。
(副委員長)1条「目的」が弱い。もう少しはっきりと条例の意義を書いた方がよい。
(委員長)パブリック・コメント手続などは、市民参加がまだ行われていなかったころのものだ。これを今やって本当に市民参加の意味があるのか疑問だ。
PDCAの各段階に分けて検討してきたのは、市政のすべての段階について知ってほしかったからだ。実施・評価段階の手続が少ないが、書くのは難しい。偏りがあるのは、今書ける具体的な手法があるかどうかの違いだ。いずれにしても市民の視点に立ち、PDCAサイクルの各段階において、それぞれ有効な市民参加の方法を考える必要がある。
(2)意見交換
講師 名古屋大学大学院法学研究科 教授 後 房雄氏
(以下、後先生のアドバイスの要点)
- 条例に何を期待するか。条例ができたからと言って、市民参加が積極的になるわけではないので、その点に関して過大な期待はしないほうがよい。あくまで出発点に過ぎない。
- 条例は抽象的にならざるをえない。条例は議会で議決が必要だから、簡単なことまで条例に書くと、ちょっとしたことでも議決が必要になる。適度に抽象的な方がよい。ワークショップや公聴会のことは、条例で書くような内容ではない。通常は、規則に書く内容だ。
- 何人かの委員さんが言ったことと同じだが、企画立案段階に偏っている。5条にPDCAの各段階が出てくるが、「広く市民の意見を反映させる」という表現は、企画立案段階をイメージした言葉だ。7条「市民参加手続の方法等」では、「1つ以上を実施」と書いているが、これも企画立案段階のことだ。そのほかも含めて、5条以外は企画立案段階に偏っているという違和感がある。
- 3条1号の「すべての市民」という表現は、子供を含んでも特に支障はない。むしろ、有権者になる前の子どもに向けて、積極的に働きかける試みがあってもよい。
- 5条に「広く反映させる」とあるが、ひどい意見は当然、取捨選択することを前提に書かないと、「俺の意見が反映されていない!」と言う人が出てくる恐れがある。
- 6条「市民参加の対象」には、市民参加を実施するものと実施しないものの両方を規定しているが、これは同じことを2度言っていることになる。1項5号があれば2項は不要で、それ以外は市長の判断でよいのではないか。
- 6条2項5号の「市税の賦課徴収」は、市民参加の対象としていないが、税が高い安いだけでも意見を聞けるのではないか?
- 具体的な手法を書くと、条例を縛ることになる。PDCAの各段階でどういうことをするのかを書いた方がよい。
- 今の段階では難しくても、今後、何ができるかを決められるようにしていくほうがよい。
- 具体的な市民参加の方法が思いつかない、中途半端な今の段階で書くと、縛られてしまう。
- 冒頭にも言ったが、条例をつくって何をするのか。既にやっている参加手続を書くだけでは現状を整理するだけだ。新たなことを書いて市や市民に投げかけるのもよいのではないかと思う。
- 本来、市民参加は、市の方針をどのように決めるかという“決定”部分(=住民投票)が重要だ。「住民投票」の結果を尊重すると書いた自治体も多い。企画立案以外を書くことが、今の時代に条例をつくる意味では?と思う。
意見交換
後先生を交え、条例の事務局案について意見交換を行った。
(委員長)先生の話にあった住民投票制度については、前回の委員会で条例に入れないことで決定している。
(委員C)「条例に期待するのはよくない」という話は、「市民は、市民参加条例に期待するな」、「行政は、市民参加条例に沿って形だけ整えれば、市民と協働でつくりましたと言える」という意味にとられかねないと思う。
(後先生)既に述べたように、市民が積極的に参加するようにならない。しかし市の側には、市民参加を宣言することとなるので市民参加の促進には効果的である。
(委員A)条例は抽象的なことを書いて、具体的なことは要綱に書くという話だが、要綱という形で行政が持っていても、市民にはわからない。一般市民の立場からすると具体的に書かれていないとよくわからない。
(後先生)やっていることが具体的に書かれていれば、市民に周知するという意味はあるが…。(委員A)それすら市民は知らない。
(後先生)今やっていることに拘るより、PDCAの新しい方法を書いて、今後の市民参加の出発点とする意味がある。
(委員A)理念型にすれば、なおさら市民参加が進まない。
(委員長)先生には「適度に抽象的がいい」と説明していただいた。前回、総合メニュー型がよいと言った人は、条例の中で「実施・評価段階については、これからメニューを考えていきます」と書くのはどうか。
(委員C)わかりやすいという意味でなら、PDCAの抽象的でないものなら、よいかもしれない。自分の考えも少しずつ変わってきている。
(委員F)理念型でもよいが、市民が参加しやすいものを。例えば、石狩市の条例「石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例」第4条には、「市民参加を推進するための制度が市民の考え方を適切に反映したものとなるよう、必要に応じ、随時その見直しを行う」と書かれている。実施・評価段階について、今はメニューに挙げられなくても、こういうものがあればよいのでは?
(後先生)総合メニュー型にしても、各段階をすべて書くことは不可能だろうと思う。
(委員A)条例の型の話ではなく、いちばん参加しやすいことが市民の側からは大事だ。まず、要綱から条例に進めたいという思いを目的に書く必要がある。
(委員I)どちらの型でもわかりにくいことは変わらない。条例は、方向性を示すだけでよいと思う。手続を網羅する必要はない。総合メニュー型でも手続の記述は不十分だと思うので、より詳しいことは別にした方がよい。
(事務局)わかりにくいという話だが、条例だけを公表するのではない。当然、条文ごとに解釈をつけて広報なりホームページなりで公表する。市民参加を推進するためには、要綱レベルも当然、公表するものだと考えている。
(後先生)メニューの細目をここまで書くかどうか。「開催日時」などを書くかどうかを問題にしている。
(委員A)私はあった方がいいと思う。ないと参加できないと思う。
(委員長)今、考えられる程度のメニューは入れてもいいのかなと思っている。
(委員B)細かい内容までは入れなくてもよいが、実施・評価段階を同程度載せられるか不明だ。市民は条例しか見ないから、条例には最低限の項目は必要だと思う。
(委員C)実施・評価段階まで参加できるようなものをある程度、メニューに載せてほしい。
(委員D)1条(目的)の「まちづくりを推進」という表現が抽象的だ。6条と結びつかない。
(事務局)実施・評価段階の手続は、事務局として思い当たるものがないので、皆さんから提案してほしい。
(委員E)9条は、傍聴者のためのものだと思う。審議会自体に参加したい人と傍聴に参加したい人があるが、まわりに重点を置く必要はないと思う。
(委員F)「条例は適度に抽象的に」と先生が言われたが、条例の型を整理しないと話が食い違ってくる。
(委員長)現行にない実施・評価段階の手続をどうするか?
(委員H)審議会等については、10条(会議録の作成および公開)以降はいらないと思う。具体的なことが書かれていないと参加できないというのは、杞憂ではないかと思う。
(委員I)市民参加条例によって「こういう市民参加ができます」ということは書きたい。
(後先生)皆さんの意見は、大きくは異なっていないと思う。PDCAに分けて具体的に書けないアンバランスは承知の上で書くことは皆さんにも異論がない。
17条(実施予定および結果の公表)をもっと重視した方がよい。「定期的に公表する」という文言をいれるなどして、今後の市民参加の充実の方向性を示すとよい。
8条(結果等の取扱い)、12条2項(パブリック・コメント手続)に書かれている、市民からもらった意見に対して、市がきちんとフィードバックするという部分は、あった方がいいと思うが、そのほかの細目は、今やっていることであって今後やらないということはありえない。今、心配する必要のない細目は、取り除いた方が、他の部分が目立つことになる。
(委員A)審議会等は、今、公開していないから、具体的に書くべきだと言っている。
(後先生)そうであれば、総括的に書いたらどうか。いちいち書くと目立ってしまう。
(委員長)後先生の話を整理すると、次のようになる。(1)各段階で市民参加を促進するという全体の流れを大きく示す。(2)アンバランスは承知の上で、書きづらいところはポイントだけでもよい。(3)17条に今後手続を考えていくことを記入しておく。(4)9条以降の細目は書かない。(委員長)今日の意見と、文末の文言の工夫を加えたい。副委員長、事務局、私の三者に今後の協議を一任してほしい。それ以外に何かあれば、事務局へ連絡してほしい。協議後、修正案を皆さんに郵送したい。
(事務局)前文をどうするかということが残っている。
(後先生)前文は置かず、市民参加の全体の流れの理念は目的に明記すればよいのではないか?
(委員C)市民の役割について、市民が納得できる内容があれば、どちらでもよいと思う。
(委員長)委員Cさんの発言は、市民が納得できれば、前文はなくてもよいと解釈してよいか。前文は置かないで、目的に、市民参加の意義をわかりやすく示すこととする。
2.その他
第7回委員会の日程調整
次回の日程を以下のとおり決定
委員会の開催日程
第7回 平成20年3月10日(月曜)、午後7時~9時
〈市役所第3分庁舎第9会議室にて〉
山内市長公室長あいさつ
条例案も目に見えるようになってきた。残り1回もよろしくお願いしたい