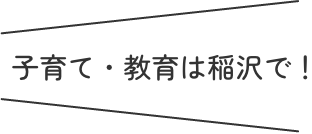平成19年度第3回市民参加条例策定委員会 会議録要旨(平成19年12月1日)
- [更新日:]
- ID:834

日時
平成19年12月1日、午後2時~4時
場所
稲沢市役所 第1分庁舎 第3会議室
出席者数
17名
政策アドバイザー1名・委員10名・市長公室長・事務局6名
(※政策アドバイザー1名は、委員を兼務しています)
傍聴者数
1名
※資料はページ下部でご覧いただけます。
市長公室長あいさつ
山内市長公室長による開会あいさつ
1.協議事項
(1)企画立案段階の市民参加の課題と方法について(※資料1)
前回検討したワークショップの内容についてまとめたものを委員長から提示し、意見交換を行った。
(委員A)前回のワークショップは、現状を批判するばかりで、前向きな部分がなかった。市民は市政に関心がないので、少数の市民の意見が通っていると思われる。市民の反応がもっとあればいい。そのことを私たち委員がどの程度まで理解しているか。もっと反応があるようなことを考えなくてはいけない。もう少し議論したい。
(委員長)前回のワークショップで出された「企画立案段階」の内容について、もう一度、各グループで議論してほしい。前向きな意見を出していきたい。
(委員B)多くの市民のニーズをきちんとつかんでいれば、一人の意見に左右されることもなくなるはずだ。
(委員A)参加意識を高めるにはどうしたらよいのだろう。
条例のタイプについて、意見交換を行った。
(委員長)まず条例をどのようなタイプにするか議論したい。条例のタイプは、(1)「理念型」、(2)「参加の手法や対象を書く、今流行の統合型」、(3)「PDCAの各段階に分けて整理し、手法の流行に左右されない新しいタイプ」があるが、どういうものにするか。
(委員C)(1)以外か。
(委員D)対象によって参加する方法を列挙するかどうかは別として、参加対象によって参加する方法をいくつか選択できるようにすべきだ。
(委員E)市民の立場に立ったとき、手法が明記されていないと足踏みしてしまう。(1)ではなく、具体的に書かれているほうがよい。
(委員F)国の法律に理念型というものは存在しないそうだ。法律は(変化する)生き物なので、詳しく書くと頻繁に条例を改正する必要がある。できれば詳しく書きたくない。
(委員A)「~型」にこだわらなくてよい。どちらかといえば「~型?」でよいのでは。
(委員長)理念型と統合型の限界が来ていると思われる。今後も議論していきたい。
「企画立案段階」の条例案を委員長から提示し、意見交換を行った。
(委員長)「市民」と「市」は、分けて書いたほうがよい。前回のワークショップで、市民の側については「市民の意識が低い」、市の側については「計画が決定してから意見を聞くのではなく、事前に市民の意見を聞く機会をつくるべきだ」という意見が出ていた。そこで、「市民」には「積極的」、「市」には「事前に」という言葉を書いた。
(委員F)「~ように努めます」という言い方も、よいかどうか検討すべきだ。
(委員A)条例制定時と状況が変わったときに、いちいち変更することにならなければよい。

2.勉強会
講師 政策アドバイザー 藤岡 喜美子 氏
(特定非営利活動法人 市民フォーラム21・NPOセンター 事務局長)
(1)ワークショップ「実施段階」について検討
- 事務局より、成人式、アダプトプログラム、まちづくり推進協議会を例に挙げて稲沢市の現状を説明(※資料2)
- 事務局の提示した事例をもとに市政の実施段階における問題点などを、2グループに分かれてワークショップ形式で検討
(2)まとめ
(委員長)終了時間となったので今回のワークショップで出た意見を発表する場面がなかった。意見をまとめて、第4回委員会で報告する。
3.その他
第4回委員会の開催日程
平成19年12月15日(土曜)午後3時から5時まで
市役所 第1分庁舎 第3会議室にて
企画課長あいさつ
杉原市長公室次長兼企画課長による閉会あいさつ