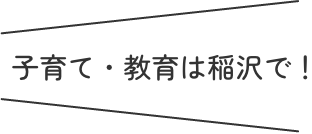公的年金等にかかる個人住民税の納付方法について
- [更新日:]
- ID:689
公的年金等にかかる所得に対する住民税は、平成21年10月より当該年金から特別徴収(天引き)されるようになっております。この制度によって、年4回の納期で納めていただいていたものが年6回(初年度は5回)になり、1回あたりに納めていただく負担が少なくなります。
対象となるかた
次の1~4のいずれにも該当するかたが対象です。
- 当該年度の4月1日時点において65歳以上のかた
- 公的年金等を受給しており、公的年金等にかかる所得に対して住民税が賦課されるかた
- 1月1日以降引き続き稲沢市内に住所を有するかた
- 介護保険料が年金から特別徴収されているかた
※ただし、次の場合は特別徴収の対象とはなりません
- 公的年金等の受給額が年額18万円未満のかた
- 特別徴収税額が公的年金等の年額を超えるかた
公的年金等から特別徴収される税額
公的年金等にかかる所得に対する住民税の所得割額および均等割額が特別徴収されます。
※給与所得など公的年金等以外に所得がある場合は、給与からの特別徴収もしくは納付書や口座振替による普通徴収により納めていただきます
対象となる年金
老齢基礎年金等
納付の方法
公的年金等にかかる税額は次のとおりとなります。
開始年度(新たに特別徴収の対象になるかた)
- 普通徴収
6月:年税額の4分の1
8月:年税額の4分の1 - 特別徴収
10月:年税額の6分の1
12月:年税額の6分の1
2月:年税額の6分の1
※年度前半において年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により納付し、年度後半については年税額から普通徴収した額を控除した額を、10月・12月・2月における公的年金等の支給月ごとに特別徴収により納付します
2年目以降(前年より継続して特別徴収の対象のかた)
特別徴収 平成28年度まで
- 仮徴収
4月:前年度2月と同じ額
6月:前年度2月と同じ額
8月:前年度2月と同じ額 - 本徴収
10月:年税額から仮徴収額を引いた残額の3分の1
12月:年税額から仮徴収額を引いた残額の3分の1
2月:年税額から仮徴収額を引いた残額の3分の1
※4月・6月・8月においては前年の10月からその翌年の3月までに納付した額を、10月・12月・2月においては年税額から仮徴収された額を控除した額の3分の1ずつを、公的年金等の支給月ごとに特別徴収により納付します
特別徴収 平成29年度以降
- 仮徴収
4月:前年度年税額の2分の1に相当する額の3分の1
6月:前年度年税額の2分の1に相当する額の3分の1
8月:前年度年税額の2分の1に相当する額の3分の1 - 本徴収
10月:年税額から仮徴収額を引いた残額の3分の1
12月:年税額から仮徴収額を引いた残額の3分の1
2月:年税額から仮徴収額を引いた残額の3分の1
年金特別徴収に関するQ&A
問1 どうして、公的年金等からの住民税の特別徴収を行うのですか?
公的年金等から住民税を納めていただくことにより、納税者が市役所の窓口や金融機関に出向く必要がなく、納め忘れもありません。また、納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担額も軽減されます。このように納税の利便性向上を目的にしたものです。
問2 特別徴収により、納付する額が多くなることはありませんか?
年税額が増えることはありません
問3 公的年金等から特別徴収をしないで、従来通り納付書で納めることはできますか?
本人の希望で納める方法を選択することはできません。地方税法により、「公的年金等所得に係る個人住民税については、年金から特別徴収の方法により徴収するものとする。」とされており、原則として、公的年金等にかかる住民税の納税義務者のうち、4月1日現在において公的年金等の支給を受けている65歳以上のかたは、特別徴収により納めていただくこととなります。
問4 障害年金を受給していますが、特別徴収の対象となりますか?
障害年金や遺族年金は住民税が課税されないため、特別徴収の対象とはなりません。特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とする年金となっています。
問5 特別徴収の対象となる年金を2種類受給していますが、どの年金から特別徴収されることとなりますか?
2種類以上の年金を受給されているかたの場合、その受給額の多少に関わらず、特別徴収を行う年金について優先順位が決められており、介護保険料と同一の高順位の1つの年金から特別徴収を行うこととなります。
問6 当初、介護保険料を公的年金等から特別徴収されていましたが、年度途中で介護保険料が変更になったため、普通徴収に切り替わりました。住民税については、引き続き特別徴収されますか?
介護保険料の特別徴収の対象者でなくなった場合は、徴収済額を除いた残額のすべてが普通徴収に切り替わることとなります。
問7 公的年金等の所得に係る特別徴収と給与所得に係る特別徴収の両方があります。住民税の均等割は、どちらから特別徴収されますか?
給与から特別徴収されます。
問8 介護保険料と国民健康保険税(後期高齢者医療保険料)の合計額が、年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険税(後期高齢者医療保険料)については、公的年金等からの特別徴収は行われず、介護保険料のみが特別徴収されることとなりますが、住民税についてはどうなりますか?
住民税については、所得税と介護保険料を差し引いた年金残額が住民税額より大きい場合は、住民税の特別徴収の対象となります。また、年金額からa)所得税、b)介護保険料、c)国民健康保険税(後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が住民税額より大きい場合についても特別徴収の対象となります。
問9 公的年金以外に給与所得がありますが、今までどおり給与からの特別徴収になりますか?
なりません。給与所得とあわせて給与からの特別徴収であったかたもすべて公的年金に係る所得に対する住民税は、公的年金からの特別徴収または普通徴収となります。