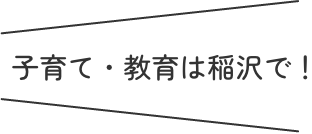祖父江のイチョウ
- [更新日:]
- ID:414

稲沢市の特産品として名高い、祖父江のぎんなん。町には樹齢100年を越えるイチョウの大木が多く存在します。
町が黄金色に染まる晩秋には、そぶえイチョウ黄葉まつりも開催されます。
イチョウの起源
イチョウは生きている化石といわれ、その起源は今から2億5千万年前の古生代末2畳紀から中生代3畳紀にさかのぼり、中生代のジュラ紀から白亜紀にかけて最も繁栄した植物の一種です。
その後新生代に入り、氷河期を迎えて絶滅した植物は少なくありません。イチョウ属の多くもこの時代に絶滅しましたが、比較的暖かかった中国中部地域の物だけが絶滅を免れ、現代に生き残ったと考えられます。このためか、中国が原産地であることが定説となっていますが、真相は定かではありません。現在、イチョウは1科1属1種です。
イチョウの来歴

イチョウが日本に渡来した時期ははっきりしませんが、中国から仏教の伝来とともに導入されたという事が定説となっています。しかし、帝国森林会編著による日本老樹名木天然記念樹(1962年)には、2000年生のイチョウが長野県にあり、1870年生が福岡県、1600年生が広島、大分に、1550年生が長崎、1500年生が富山と高知の諸県にあるとされています。
祖父江町には樹齢100年を超えるイチョウの大木が数多く存在し、晩秋になると黄金色に染まったイチョウの立ち並んだ素晴らしい風景が一望できます。この地域には伊吹おろしが吹きつけるため、防風林を兼ねて、古くから神社・仏閣・屋敷まわりにイチョウが植えられてきました。現在この実を収穫調整して出荷していることから、祖父江町のギンナンは「屋敷ギンナン」と言われています。
ギンナン生産を目的とした栽培は祖父江町が最も古いとされていますが、その歴史は意外と新しく、当町の古老の話では100年ほど前だということです。次第に大粒種の穂木が広まり、集落全体に普及していきました。その当時接木された100年以上と思われる大樹が、今も多くの実をつけています。
このようなことから、食用を目的に品種の選抜、淘汰が行われてきました。祖父江町内で栽培されている品種には久寿(久治)、金兵衛、藤九郎、栄神などがあります。
ぎんなんの主な品種
| 品種 | 硬核期~成熟期 | 果樹の大小 | 果形 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| 金兵衛 | 7月中旬~ | 中 | 長円形 | 育成地は愛知県祖父江町。樹生はやや弱く若木の時から開張しやすい。結実樹齢は接木後3~4年と最も早い。硬核期が早く、早出しギンナンとして7月から出荷される。貯蔵性も高く、4月まで出荷できる。 |
| 久寿(久治) | 8月中旬~10月上旬 | 大 | 丸形 | 育成地は愛知県祖父江町。若木の時は直立性であるが、次第に開張する。結実期に入るのが早く、高接ぎ後5~6年で結実を始める。もっちりとした食感で苦みが少ない。粒揃いが良く、市場性も高いが、貯蔵性に欠ける。 |
| 藤九郎 | 8月下旬~10月中旬 | 大 | 丸形 | 育成地は岐阜県本巣郡穂積町。樹勢は旺盛で高木になり、結実期に入るのが6~8年とやや遅い。殻が薄いので割れやすく、早出し用には不向きである。実は最も大きく、種皮も白く美しい。貯蔵性が高い。 |
| 栄神 | 8月上旬~10月中旬 | 中 | 長円形 | 育成地は愛知県祖父江町。樹勢は強くやや開張性で、他の品種に比べて落葉期が1ヶ月程遅い。実の胴張りが良く、凹凸が少ない。貯蔵性もあり、4月頃まで出荷できる。 |
「祖父江ぎんなん」は、商標法に基づく地域団体商標です。詳しくは下記ホームページをご覧ください。